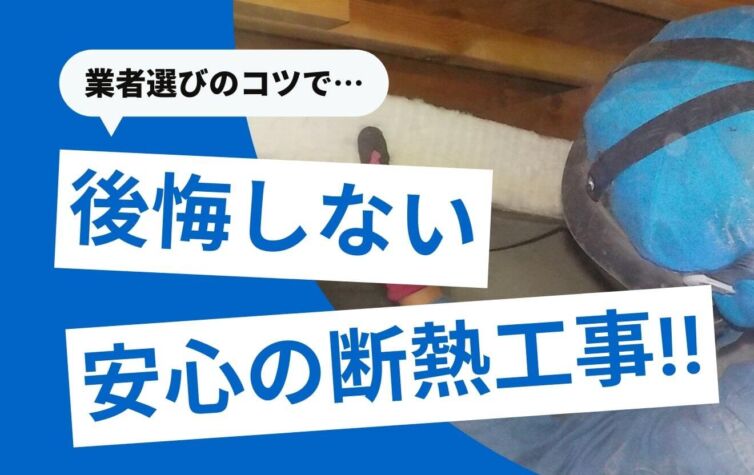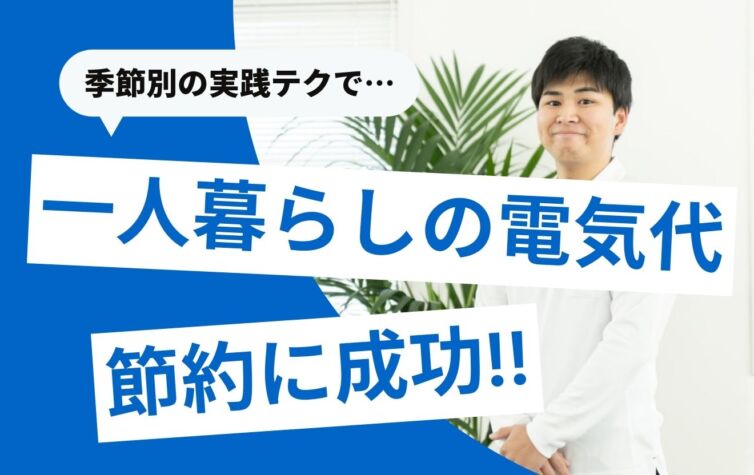「グラスウールは良い断熱材って聞いたけど本当?」
「断熱リフォームしたいけど断熱材はどれがいい?」
あなたも同じような疑問を抱えていませんか。築年数の経った住宅では、冬の寒さや夏の暑さに悩まされながらも、断熱材の種類や性能の違いがわからず、「結局どれを選べばいいの?」と迷う方がたくさんいらっしゃいます。
グラスウールのほか、断熱材の性能や使われ方について、正確な情報を知る機会は意外と少ないものです。他の断熱材と比べて、どのような特徴があるのか、きちんと理解してから選択したいですよね。
私たちヤマト産業では、京都を中心に30年以上にわたって断熱リフォームを手がけ、グラスウールをはじめ様々な断熱材での施工を経験してきました。一人ひとりの住宅の状況やご希望、ご予算に応じて、最適な断熱材をご提案することを心がけています。
この記事では、グラスウールの仕組みや種類、メリットデメリット、そして他の断熱材との客観的な比較について、わかりやすく解説していきます。
断熱材選びで迷っている方、グラスウールについて正しく知りたい方にとって、良い判断材料となり、あなたの住まいで最適な断熱リフォームの実現につながれば幸いです。
も く じ
Toggleグラスウールとは?どんな断熱材なの?

グラスウールとは、ガラスを原料とした繊維状の断熱材のことです。見た目はまるで雲のようにふわふわしていて、触るとちくちくします。
現在では袋に入ったタイプ、ボード状に固めたタイプ、吹き込み用のバラ状タイプなど、複数の形状で販売されており、施工場所に合わせて選べるのも特徴の1つです。
また、原料の大部分がリサイクルガラスなので環境に優しく、軽量で加工しやすいため、リフォームの現場でも比較的取り扱いやすいです。現代の住宅事情にもマッチしている断熱材といえるでしょう。
グラスウールは歴史のある断熱材ですが、実は現在でも住宅断熱の主力として幅広く使われている優秀な素材です。
グラスウールの断熱の仕組みは?
「なぜガラス繊維が家の断熱を高めてくれるの?」この疑問の答えはグラスウールの構造にあります。
グラスウールのガラス繊維1本1本は非常に細く、これらの細かな繊維がふんわりと絡み合うことで、無数の小さな空気の層が生まれます。この無数の空気層こそが、グラスウールの断熱性能の源です。
動かない空気は熱を伝えにくい性質があるため、この微細な空気層がたくさんあるほど、優れた断熱性能を発揮するという仕組み。グラスウールの繊維に挟まれた空気は動きが制限されるため、外部からの熱が室内に伝わりにくくなるのです。
つまり、グラスウール自体が断熱しているのではなく、繊維の間に閉じ込められた「動かない空気」が断熱の主役というわけです。この原理は羽毛布団と似ていて、細かい繊維がたくさんの空気を抱え込むことで、優れた断熱性を発揮しています。
グラスウールの種類と密度による違い
一口にグラスウールといっても、実は密度によっていくつかの種類に分けられます。10・16・20・24・32Kなどこの密度の違いが、断熱性能と価格に影響するので、しっかり理解しておきましょう。
- 一般的なグラスウール
特徴:最もスタンダードなタイプで価格が安い
繊維:太めで密度も低く、空気層は大きめ
断熱性能:十分な性能はあるが、高性能タイプには劣る - 高性能グラスウール
特徴:密度を高めた高性能タイプ
繊維:より細く、多くの細かな空気層を形成
断熱性能:同じ厚みでも一般タイプより高性能
密度が高いほど断熱性能も向上しますが、その分コストもアップします。ご予算と求める性能のバランスを考えて選ぶことが大切ですね。

グラスウールはどこの断熱に使われる?
グラスウールの使用場所は、主に壁・天井・屋根・床下の4箇所。それぞれの場所で、最適な形状のグラスウールが使い分けられています。
例をあげると、
- 壁の断熱では
「袋入りグラスウール」を柱と柱の間に充填する方法が採用されることが多いです。袋があることで施工時の飛散を防ぎ、湿気からも保護できるメリットがあります。 - 床下の断熱では
「ボード状グラスウール」を床材の下や床下の根太間に設置することが多いです。形が崩れにくく、ボード状で施工しやすいメリットがあります。
どの場所でも共通しているのは、隙間なく施工することが重要だということ。わずかな隙間があるだけで断熱効果は低下してしまうため、プロの技術が求められる分野でもあります。
以上、グラスウールは価格と性能のバランスが取れた、現在でも多くの住宅で採用されている断熱材です。正しく施工すれば、冬の寒さや夏の暑さを効果的に遮断し、光熱費の削減も期待できる優秀な素材といえるでしょう。
グラスウールのメリットデメリットは?
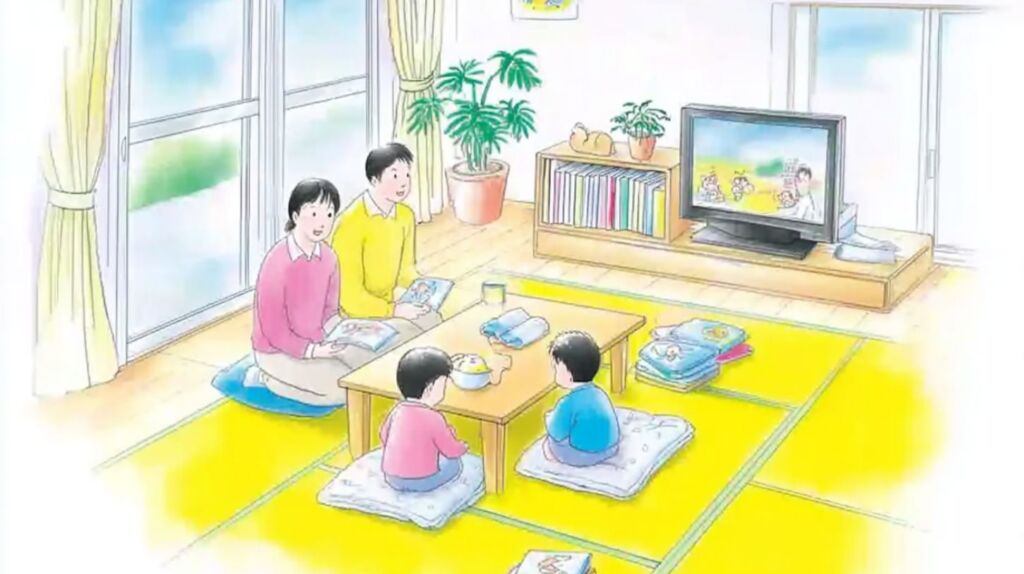
断熱材選びで迷っている方にとって、メリットとデメリットをしっかり把握することは重要ですよね。ここでは、グラスウールの良い面も気になる面も、包み隠さずお伝えします。
メリット5つ
まずは、グラスウールのメリットから見ていきましょう。
1.コスパが良い
グラスウールの魅力は、何といってもコストパフォーマンスの高さです。他の断熱材と比べて材料費が安く、限られた予算でも十分な断熱効果を実現できます。「できるだけ費用を抑えて断熱性能を向上させたい」という方にとって、グラスウールはとても魅力的な選択肢といえるでしょう。
また、全国どこでも手に入りやすく、施工できる業者が多いため、競争原理なども働いて工事費用も抑えられる傾向にあります。
2.防音効果もある
グラスウールは断熱材としてだけでなく、優れた防音材としても機能します。内部の繊維が吸音してくれるため、外からの騒音を軽減したり、室内の音漏れを防いだりする効果が期待できます。
音楽を楽しむ方や、小さなお子さんがいるご家庭では、この防音効果も大きなメリットとして感じられるはずです。断熱と防音、2つの効果を同時に得られるのは嬉しいポイントですね。
3.不燃性で燃えにくい
安全面でも、グラスウールは優秀な断熱材です。主原料がガラスという不燃材料のため、耐火性に優れています。万が一火災が発生した場合でも、燃え広がりの抑制が期待でき、避難時間を確保しやすいでしょう。
家族の安全を第一に考える方にとって、この不燃性は大きな安心材料といえます。
4.自然や環境に優しい
意外に知られていないのが、グラスウールの環境への配慮です。主原料のほとんどは、家庭などから回収されたリサイクルガラスを使用しています。つまり、捨てられるはずだったガラス瓶などが、住宅の断熱材として生まれ変わっているのです。
地球環境に配慮したリフォームを考えている方にとって、この点は見逃せないメリットといえるでしょう。
5.害虫被害が少ない
グラスウールはガラス繊維でできているため、シロアリや他の害虫が好むものではありません。木質系の断熱材の場合、湿気や経年により害虫の餌となったり、巣作りの場所として狙われたりするリスクがあります。
築年数の経った住宅では、シロアリ被害への不安を抱えている方も多いでしょう。断熱リフォームと同時に害虫対策も考えられるグラスウールなら、一石二鳥の効果が期待できますね。

デメリット3つ
良い面ばかりではありません。グラスウールにもいくつかのデメリットがあります。
1.湿気に弱い
グラスウールの弱点は、湿気への弱さです。水分を含んでしまうと、せっかくの空気層がつぶれて断熱性能が低下するおそれがあります。
特に床下や外壁など、湿気の多い場所に施工する際は要注意。適切な防湿シートの設置や通気工法の採用など、確立された湿気対策をしっかり行う必要があるでしょう。
また、長期間湿った状態が続くと、汚れの付着や型崩れから性能が著しく低下する場合もあるため、施工時の雨対策も重要になってきます。
2.施工に技術がいる
グラスウールは材料自体は扱いやすいのですが、その効果を最大限発揮させるには、高い施工技術が必要です。誤った施工方法では、隙間ができやすく、そこから冷気や熱気が侵入してしまうからです。
特に注意が必要なのは以下のポイントです。
- 柱や梁との接触部分の隙間処理
- 配管周りの複雑な形状への対応
- 適切な厚みと密度での施工
- 圧縮しすぎないよう注意深い取り付け
DIYで施工する方もおられますが、断熱材の性能を十分に活かすためには、やはり経験豊富な専門業者に依頼することをおすすめします。
3.経年により沈下の可能性
グラスウール自体は劣化しにくい素材ですが、施工不良や湿気の影響により、時間が経つにつれて沈下するおそれがあります。特に壁内に縦に施工された場合、上部に隙間ができて断熱性能が低下することも考えられるでしょう。
この沈下を防ぐためには、支持材の設置や、密度の高いグラスウールの選択が効果的です。また、定期的な点検により、必要に応じて補修や交換を行うことも大切になります。
とはいえ、適切に施工されたグラスウールであれば、20年、30年、条件によってはそれ以上にわたり安定した断熱性能を維持できる場合があるのも事実。施工の質とメンテナンス計画に配慮しておけば、長期的に安心して使用できる断熱材です。
以上、グラスウールのメリットデメリットをまとめて紹介しました。
確かにデメリットもありますが、それを上回る多くのメリットがあります。特に限られた予算で効果的な断熱リフォームを実現したい方にとって、おすすめしたい選択肢の1つといえるでしょう。
グラスウールにすべき?他の断熱材との比較

グラスウールと他の断熱材のどれを選べばいいか、多くの方が悩むポイントですよね。
ここでは、住宅でよく使われる3つの断熱材「グラスウール・発泡ウレタン・セルロースファイバー」を、5つの重要な項目「断熱性・気密性・耐久性・防水性・価格」で比較してみましょう。
- グラスウール
リサイクルガラスを高温で溶かして細い繊維状に加工した断熱材のこと。繊維の間に無数の小さな空気層ができることで断熱効果を発揮し、軽量で扱いやすいのが特徴です。 - 発泡ウレタン
液体状の材料を現場で発泡させて施工する断熱材のこと。構造材にぴったりと密着するため、隙間ができにくく高い気密性を実現できます。 - セルロースファイバー
新聞紙などの再生紙を細かく砕いて繊維状にした断熱材のこと。機械で吹き込んで施工するため、複雑な形状でも隙間なく充填できる環境配慮型の素材です。
①断熱性
【グラスウール】
一般的な住宅断熱には十分な性能を備えています。特に高性能タイプ(24K、32Kなど)になると、より優れた断熱効果が期待できます。
密度が増すことで断熱性能をさらに高められるため、予算と相談しながら必要な性能を検討しやすいのが特徴。ただし、施工時の隙間や圧縮により性能が左右されやすい点には注意が必要です。
【発泡ウレタン】
この3つの中では優秀な断熱性能を誇ります。現場で発泡するため隙間なく施工でき、本来の性能を発揮しやすいのが大きなメリット。
薄い厚みでも高い断熱効果が期待できるため、施工スペースが限られている場所でも効果を発揮します。
【セルロースファイバー】
グラスウールと同程度の断熱性能です。新聞紙などの再生紙を原料としているため、繊維内に含まれる空気が断熱効果を生み出します。
吹き込み施工により隙間を埋めやすく、複雑な形状でも均一な断熱層を形成できるのが特徴です。
②気密性
【グラスウール】
充填式施工のため、施工条件によってはどうしても隙間ができやすく、気密性は3つの中では劣ります。柱や梁との接合部分、配管周りなどで隙間ができると、そこから空気が漏れて断熱効果が低下するおそれがあります。
ただし、丁寧な施工と適切な気密シートなどの施工により、十分な気密性を確保することは可能です。
【発泡ウレタン】
現場で発泡させながら施工するため、構造材にぴったりと密着し、非常に高い気密性の実現が期待できます。冷気や暖気の侵入・流出を効果的に防ぐことができ、3つの中ではとても優秀です。
特に床下施工では、この密着性の高さが大きなアドバンテージとなります。
【セルロースファイバー】
吹き込み施工により細かな隙間まで充填されるため、グラスウールより高い気密性が期待できます。ただし、発泡ウレタンほどの密着性はありません。
施工技術により仕上がりに差が出やすく、経験豊富な施工業者選びが重要になります。
③耐久性
【グラスウール】
ガラス繊維のため、腐食や劣化に強く、適切な環境であれば30年以上の長期間にわたって性能を維持でき、条件によってはそれ以上の使用も可能です。ただし、湿気には弱く、結露などで濡れると性能が低下するリスクがあります。
また、施工不良や湿気の影響により沈下する可能性があるため、定期的な点検が推奨されます。
【発泡ウレタン】
化学的に安定した素材のため、腐食や虫害に強く、長期間の使用にも耐えます。一度発泡・固化すると形状が安定し、沈下の心配もほとんどありません。
ただし、紫外線には弱いため、直射日光が当たる場所では劣化が進みやすくなります。
【セルロースファイバー】
紙が原料のため、本来であれば虫害や腐食のリスクがありますが、ホウ酸などの防虫・防腐処理により、これらの問題をクリアしています。適切に処理されたものであれば、長期の耐久性も期待できるでしょう。
ただし、湿気に対してはグラスウール同様に注意が必要です。
④防水性
【グラスウール】
ガラス繊維自体は水分を吸収しませんが、繊維間に水分が入り込み、水を含んだ状態が続くと、型崩れや汚れの付着により性能低下のリスクがあります。そのため、防湿対策や適切な通気の確保が不可欠です。
【発泡ウレタン】
構造上、水分の侵入を効果的に防ぎます。3つの中では防水性に優れており、多少の湿気では性能が低下しません。ただし、完全防水ではないため、継続的な水分にさらされる環境では注意が必要です。
【セルロースファイバー】
紙が原料のため、本質的には水分に弱い素材です。ただし、撥水処理により一定の防水性を持たすことができます。短時間の湿気であれば問題は少ないですが、長期間の湿潤環境では劣化のリスクがあります。
➄価格
【グラスウール】
3つの中では最も安価な断熱材です。施工費を含めても、他の断熱材より大幅にコストを抑えられます。予算が限られている方や、広い面積の断熱を行いたい方には良い選択肢といえるでしょう。
【発泡ウレタン】
グラスウールと比べて高値になります。専用の機材と技術が必要なため、施工費も高めになりがちです。ただし、高い性能を考慮すれば、コストパフォーマンスは決して悪くありません。
【セルロースファイバー】
吹き込み施工のため、施工の難易度が高く、専用機材が必要なため、施工費はやや高めです。環境配慮と性能のバランスを重視する方に選ばれることが多い断熱材になります。
※実際の価格は、断熱材の密度・施工条件・各施工業者によって大きく異なります。
以上、グラスウールと他の断熱材(発泡ウレタン、セルロースファイバー)、それぞれの特徴を比較して解説しました。各項目は、密度や厚み、環境の他、施工技術によっても差が出ますが、おおよその目安を比較表にまとめてみました。
| 項目 | グラスウール | 発泡ウレタン | セルロース ファイバー |
|---|---|---|---|
| 断熱性 | 〇~◎ | ◎ | 〇 |
| 気密性 | △~〇 | ◎ | 〇 |
| 耐久性 | ◎ | ◎ | 〇 |
| 防水性 | △ | 〇 | △ |
| 価格 | ◎ (安い) | △ (高い) | 〇 |
このように、それぞれの断熱材には特徴があります。グラスウールは価格面で有利な一方、発泡ウレタンは性能面で優秀。セルロースファイバーは環境配慮の面などに優れていますが、施工費が比較的高くなります。
どの断熱材が最適かは、お住まいの構造や築年数、ご予算、そして何を重視するかによって変わってきます。最終的には、住宅の状況やご希望をしっかりとお聞きした上で、最適な断熱材をご提案させていただくのが一番。まずはお気軽にご相談いただければと思います。
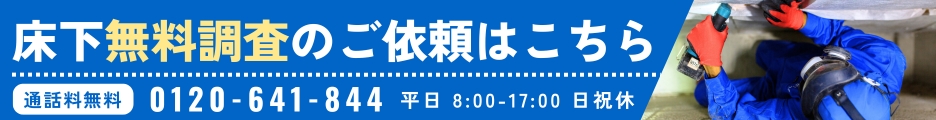
まとめ:断熱リフォームで住まいの悩みを解決しよう

ここまでグラスウールの特徴や他の断熱材との比較をお伝えしてきました。ご希望の予算でしっかり断熱効果を得たい方にとって、グラスウールはとても有力な選択肢です。
そして、嬉しいニュースがあります。2025年は断熱リフォームに対する補助金制度もあるので、うまく活用すれば、費用負担を軽減しながら効果的な断熱改修が実現できそうですね。
2025年に利用できる主要な補助金制度
断熱材を使ったリフォームで活用できる国の補助金制度には、主に以下があります。
【断熱材の施工に使える補助金】
- 子育てグリーン住宅支援事業(国交省、環境省)
→ 開口部や躯体の断熱改修・エコ住宅設備の設置などが対象 - 既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省)
→ 断熱材・窓・ガラスを対象とした独立制度
【その他の断熱、省エネ関連補助金】※主に窓や設備向け
- 先進的窓リノベ2025事業
→ 窓・ドアの断熱改修が中心 - 給湯省エネ2025事業
→ 高効率給湯器の導入支援
国の補助金制度以外に、各自治体が独自で制度を実施している場合もあるため、お住まいの地域でどのような制度があるのか、ぜひ一度確認してみてください。
まずは無料診断で現状を把握しましょう
2025年は断熱リフォームを始めるのに良いタイミングです。快適で省エネな住まいへの第一歩は、正しい情報収集から。賢く補助金を活用して、理想の住環境を手に入れてください。
最後に、冬の底冷えや夏のむし暑さ、光熱費の高さでお困りの方は、一度専門家による診断を受けてみることをおすすめします。ヤマト産業では、お住まいの断熱性能を調べる無料調査を行なっています。
この調査では、現在の断熱状況を詳しく診断し、グラスウールを含めた様々な断熱材の中から最適なプランをご提案いたします。また、活用できる補助金制度も合わせてご案内するため、コストを抑えた効果的な断熱リフォームも実現可能です。
強引な売り込みは一切行いません。まずはあなたのお家がなぜ寒いのか、なぜ暑いのかの原因を知ることから始めてみませんか?断熱材の選択で迷っている方も、補助金の活用を検討中の方も、お気軽にご相談ください。
快適で省エネな住まいへの道筋が、きっと見えてくるはずです!